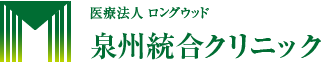院長ブログ
Vol.68 更年期障害の仕組み・・・更年期不調の原因はホルモンのみにあらず
2025年06月13日
更年期障害の定義
更年期不調の中でホットフラッシュ(のぼせ)は良く知られていますが、それ以外にも倦怠感、抑鬱など、とにかくこれと言った原因が思い当たらないのに、いつもの調子と異なる状態になると「あら?私、更年期かしら?」という話しになります。ここでまず、前提を確認をしておかなければならないのですが、更年期障害とは「閉経に伴う諸症状」の事を言い、ホットフラッシュを感じたとしても、70歳や30歳(早期閉経をのぞく)では更年期障害とは言いません。更年期障害とは、閉経前後にともなう、体調不良の諸症状の事を言います。
しかし、更年期ではないのに、更年期によく見られるような不調を感じることはしばしばありますので、ホットフラッシュや倦怠感、抑鬱などの症状は、確かに更年期に増えるのは事実ですが、更年期特有の症状ではないということになります。裏を返せば、更年期の諸症状は、女性ホルモンの減少はその要因の一つではあるものの、ホルモンのみが原因ではないことを意味しています。では、どういった理由でホットフラッシュや、倦怠感、抑鬱のような症状がでるのでしょうか。次にその理由をお話ししましょう。
倦怠感・抑鬱の構造
ホットフラッシュの説明に入る前に、まず倦怠感を生み出す身心の消耗についてふれておきます。更年期症状としての倦怠感と抑鬱は実は同じ事象を違う側面から見たものと言えます。倦怠感は身体が感じている消耗、抑鬱は心が感じている消耗で、いずれも身心の気力が低下した状態です。下記の図を見て下さい。消化力が低下するとエネルギーの供給が低下して気力が萎えます。「腹が減っては戦はできぬ」ですね。また、いくら腹ごしらえをしても、一日中悩み事で頭を使ったり、朝から晩まで肉体労働を休みなく続け、それが途切れることなく連日続く状態では心も身体も休まらずにすり減っていきます。生活している環境が酷暑、極寒、高湿度だったり、人間関係に挟まれて気を使う状況が続いていたり、誰かに責められ続けていてもやはり消耗します。その結果として、疲れが抜けない、やる気が出ないという状態に陥っていくわけですね。これは、更年期に限らず、慢性疲労では全般的に見受けられる構図です。もちろん、慢性疲労の背後に炎症が隠れていることもありますし、二次的な抑鬱ではなくて真性の鬱病が隠れていることもありますが、過半数以上のケースではこの構造が成り立ちます。

ホットフラッシュが出る仕組み
さて、慢性の倦怠感の構造が理解出来たところでホットフラッシュ(のぼせ)について説明を致します。ホットフラッシュは身体の消耗もしくは、年齢とともに低下する体力が関係しています。もちろん、局所でみると、末梢血管が開いて暑さを感じるなどの現象はありますが、ホットフラッシュ現象を理解するにはもっと大きな視野で観察する必要があります。ホットフラッシュ現象には基本的には下記の2つの要素が関係しています。
- 陰虚火旺
- 下肢の冷え
陰虚火旺とは端的に言えば、身体が陰虚(消耗)し、火旺(気力)で頑張る状態です。この状態を悪化させる要因として下記の二つの要素があります。
①ー1 相対的(若い頃と比べて)体力減少
①ー2 暇が苦手な性格(頭が忙しい)
頭は年を取りませんが、40歳を過ぎると意識的に身体の手入れをして体力維持に努めなければ、自然と身体は衰えていきます。そうすると、頭と体の間にギャップが生まれていきます。落ちた体力を受け入れて少しゆっくりした生活を選べば、帳尻が合うのですが、暇が苦手な性格で常に、次はなにをしなければ、あれをしなければと頭が忙しいと、衰えた体に鞭を打つ(気合いでカバー)することになります。これが陰虚火旺を煽ることになるわけです。
次に、下肢の冷えが関係します。体の冷えを知覚すると、体はそれを温めようとします。熱い空気は上昇するのと同じく、下肢を温めようとした反応は、結果として上半身に熱を送り出します。これによってのぼせを生じる前提条件が整うわけです。あたかも、コップいっぱいに注いだ水をほんの少し揺らすと一気にこぼれ出すのと同じく、このギリギリな状態に対して、急な温度変化(外から家の中に入る、またはその逆)やふとした急な動き、急な心の変化(些細なことでも)をきっかけとしてバッとのぼせが出る事になります。漢方薬を使うならば、この陰虚火旺を治める三物黄岑湯という処方になりますが、この構造を知って、少しゆったりとした生活を心掛け、足湯をして足元の冷えを解消する、普段から足腰を使って下肢を鍛えておくなどの養生をすると症状は格段に減ります。
消化力は全てに通じる
下図をご覧下さい。人間が生きて行くためには何かを食べ、それを消化して栄養にし、エネルギーをめぐらさなくてはなりません。この大元である消化力が低下をするとあらゆる生命活動が低下します。

思考力から気力体力、行動力に至るまで。集中力は耐える力、そして体の保湿力や保温力も。それゆえ、消化機能が低下すると、体は冷え、思考力は低下し、行動する意欲はなくなっていきます。これは、最初の気力の説明図でもお話しした内容に繋がっていますね。実際に、更年期不調を強く訴える女性を診察してみると、消化力が低下した人が多いです。消化力を整える為には「養生のキホン」
https://www.longwood-senshu-cl.com/%E9%A4%8A%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%83%B3.pdf
を守る必要があるのですが、この説明は別の機会に詳しくすることにしましょう。
更年期障害の構造
これまで述べてきたように、更年期の症状には、それに至るプロセスが存在し、その意味を知っていれば薬を使わずとも対処が可能です。以下に、典型的な更年期障害の構造図をしめします。

先に説明したように、消化力の低下が下半身の冷えを引き起こします。下半身が冷えることでホットフラッシュ症状が強くなります。また、意識的に運動を心掛けるなどの努力をしていなければ、体力が低下をしてきます。実は眠りには体力が関係していて、体力が低下すると眠りが浅くなります。そう、寝る子は育つと言いますが、健康で良く食べ、よく走り回る子はよく寝ます。逆に神経質で食の細い子は眠りが浅くなる。高齢者になるほど眠りが浅くなる、といった感じです。そのような状況下、追い打ちをかけるように社会的な負担が増えます。子育てに加えて親の介護と息つく暇もありません。日頃の生活に忙殺されている間に気が付けば50歳を黙然とし、自分の人生は果たしてこれで良かったのだろうかと振り返り、焦りや焦燥感、不安が巻き起こります。そんな中に閉経というイベントが重なりホルモンの変動という負荷がかかるわけです。この図には、不具合発生線という赤線が書いてありますが、この赤線を越えると一気に不調が沸きだしてくるのですね。それゆえ、赤線を越えなければ、女性ホルモンが減っても症状は出ませんし、逆に赤線を越えてしまえば、ホルモンに関係なく症状が出ることになります。
更年期不調の原因はホルモンのみにあらず
更年期不調の原因はホルモンのみにあらず。実は、日頃の養生と毎日の過ごし方次第では、更年期不調なく更年期を過ごすことができる。むしろ、毎月の月経で消耗することがなくなるからむしろ元気になる可能性もある。そう言う事なのです。